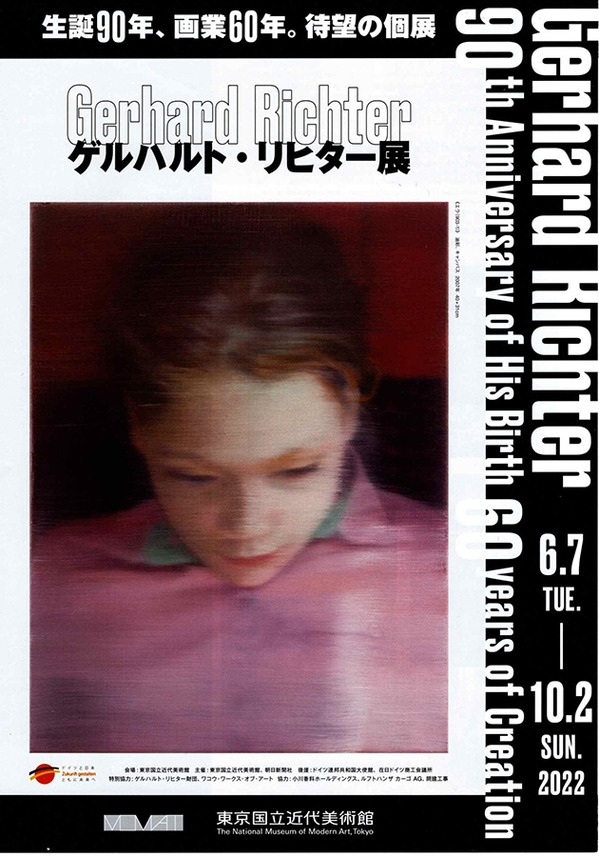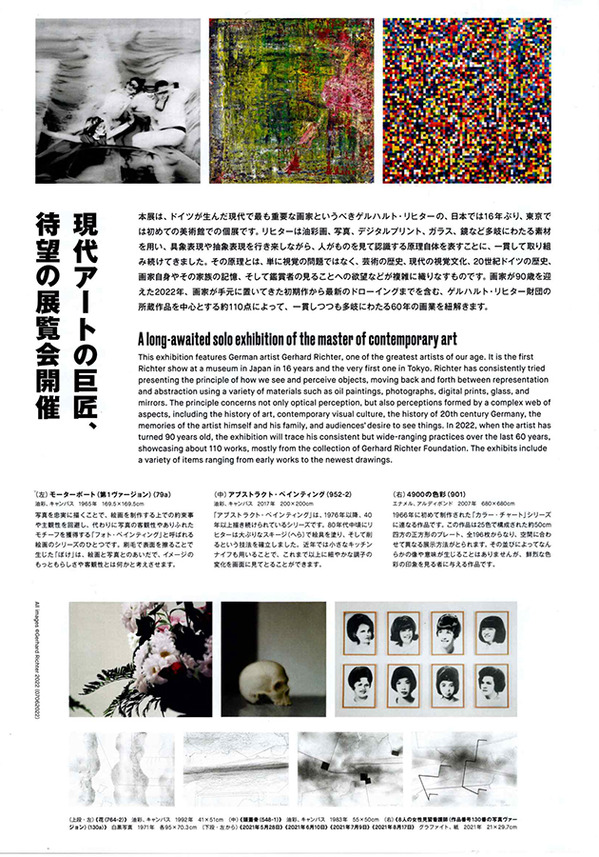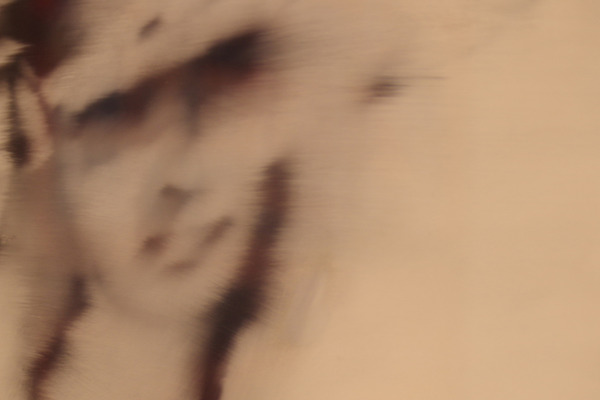hanauta
【ART】東京国立近代美術館/ゲルハルト・リヒター展
2022年6月22日
ランチの後はほど近い東京国立近代美術館へ。つい半年前ほどに「民藝の100年展」で訪れましたが、今回の目的は…
ドイツを代表する現代アーティスト、ゲルハルト・リヒターの大回顧展です。日本では16年ぶりと謳っていたので記憶を辿ると、その時も川村記念美術館に2人で行ったではないですか!先日のポーラ美術館など企画展で作品を見る機会も多いので、それほどの期間が空いていたとは思ってもいませんでした。
《今展覧会のフライヤー・オモテ面》
東ドイツで生まれて壁画〜として生活していたリヒターは旅行で訪れた西ドイツで見た抽象表現主義に強い影響を受け、ベルリンの壁が建設される半年前の29歳の頃に西ドイツ・デュッセルドルフへと移住します。
《今展覧会のフライヤー・ウラ面》
今回はリヒター自身が模型や図面を作り展示構成を考えたというから、なんて贅沢な!これは今を共に生きるアーティストならではですね〜。
会場に入ってすぐ目の前に広がる空間(作品数点を除いて撮影可能でした)。よくある年代順でもなく、数あるシリーズごとでもなく(比較的シリーズでまとまってはいますが)、並び順にも作者の思いが込められていると思うとその不規則性にも意味を考えてしまいます。
最初の部屋はアブストラクト・ペインティングを中心に展示。1970年代後半から40年に渡り描かれ続けたリヒターを代表するシリーズです。絵の具をたっぷりと塗ったカンバスをヘラやスキージで削ぎ落とす手法で、偶然に発生したイメージは自身の予想しないものへと展開していきます。
《アブストラクト・ペインティング》
こちらは2016年の作品で、作家蔵となっていたので手放さずに手元に置いていたもの。通常の回顧展は世界に散らばった作品を集めて展示されていることがほとんどですが、今回は自身が持っていたもの、そして財団コレクションからの作品が一堂に会したスペシャルな展示なのです。
初期のものと比べてより繊細に感じるのは、キッチンナイフを使ってより軽やかになっているからか。
《アブストラクト・ペインティング》
そしてこの2017年の作品を最後の大型絵画とすることを宣言。オーディオガイドから聞こえるグレン・グールドが奏でるバッハ「ゴルトベルク変奏曲」を聴きながら、じっくり作品と向かい合いました。
《8枚のガラス》
反射や光の透過を変えた8枚のガラス、そしてそこに映し出される周囲の様子。それらを含めたすべてを作品として観ると、光や作者の手を離れた偶然性など、他の作品と共通するテーマが現れてきます。現代アートは単に美しいものを鑑賞するのではなく、描くということや見るということなどの本質を突き詰めていたりと、見る前に少しの知識があればより深く理解できることが面白くもあり、難解と思われる理由でもあるのでしょうね。
《4900の色彩》
色見本を偶発的に並べたカラーチャートのシリーズ。こちらはケルン大聖堂の修復の際に依頼されたステンドグラスのデザインする中で生まれたものだそう。画像でしか見たことのない大聖堂のステンドグラス、光が透過した時の美しさは息を呑むほどで、いつか実際に見てみたいと思わずにはいられませんでした。
左《アブストラクト・ペインティング》、右《グレイ》
カラーチャートの対面に飾られたのは、一転してグレイ一色。
《ヴァルトハウス》
先に進んでいくと、私たちの一番好きなシリーズであるフォト・ペインティングが中心の部屋へ。新聞や雑誌に掲載された写真を正確に写し描くシリーズで、構図や構成を自らが選ばないことで作家の意思を離れた”描くこと”に専念したシリーズとなっています。
左より《不法に占拠された家》《アブストラクト・ペインティング》《頭蓋骨》
同じくフォト・ペインティングによる風景画に静物画、その間にアブストラクト・ペインティングを配置。写真が生まれて以降の”描くということ”の本質を考え続けた彼の作品群です。
写真そのままをリアルに描くのではなく”ボケ”や"ブレ"を加えてを描くこと。リアルな景色を切り取った写真をそのまま描くだけでは単なる風景画と変わりないのに、そこにブレが生じることで ”リアルな景色” ではなく ”写真のようだ” と捉え方が変わるのはなんだか面白いと感じます。
左より《モーリッツ》《エラ》《トルソ》《水溶者(小)》
自身の子供たちと妻を描いたもの。こちらも撮影した写真からの模写で、それゆえなのか家族を描くという親密性から一歩引いた不思議な距離感を感じます。
左より《モーターボート》《アンテリオ・ガラス》
フォト・ペインティングの代表作と、横には同じサイズのガラス作品を設置。ガラスに対面に置かれた作品とそれを鑑賞する人が映り込むことで、その虚いゆく景色自体を作品にしています。これも "絵画とは" の問いのひとつの答えとして描かないことを選んだ作品なのでしょうね。
フォト・ペインティングの近くで見ると分かる刷毛目、久しぶりの再会でも変わらぬ衝撃です。
《ストリップ》
こちらが先ほどの《アンテリオ・ガラス》に映り込んでいた大型作品。ここまでをすべて計算して会場構成しているのだから、何ひとつ見逃せません。。
《ビルケナウ》
この4点の大型作品はリヒターの達成点、この作品をバラバラにさせないために財団が設立したというのだから、その重要性が分かります。アウシュビッツ=ビルケナウ収容所で密かに撮られた4枚の写真をもとに、はじめはフォト・ペインティンによって描かれたのだそう。しかし途中で描くことを断念して、抽象絵画として塗りつぶして作品を完成させました。この時代にドイツで生を受けたアーティストとして、ホロコーストを題材とすることがいかに重いことかを強く感じます。。そして同じテーマでも異なるアプローチをするボルタンスキーを、ふと思い出したのでした。
《グレイの鏡》
会場全体をみるとビルケナウ(右)の対面に写真バージョン(左)、それらを映すように真ん中にグレイの鏡が設置されています。この展覧会は豊田市美術館に巡回の予定なので、そこではどの部屋でどう展示されるのだろうと気になります。
《ドローイング》
小品のドローイングでおしまい。2020年秋に「もう絵は描かない」と宣言したリヒターでしたが、このドローイングは2021年の作品!? まるで息をするのと同じであるかのように、描くことは生きることなのかしらと思い会場を後にしたのでした。
- New Entry
- Category
- Backnumber
-
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月